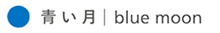ポルトガル人が愛する「3つのF」と言うものがある(1960年代のサラザールの独裁政権時代、民衆を政治から遠ざける為に利用したとも)。ひとつめのFが、「ファド」。ポルトガルの民族歌謡。どこか郷愁を帯びていて、ポルトガルギターの伴奏に合わせ、夜な夜な酒場などで歌われている。ふたつめのFが、「ファティマ」。ポルトガル中部の街で、聖母マリアが降臨した奇跡の地として、多くの巡礼者が訪れる。三つ目のFが、「フットボール(サッカー)」。これには僕も可笑しいほどに、虜になっていて、ほぼ毎日、かかさずポルトガルのスポーツ新聞に目を通している。サラザールは民衆から政治を遠ざけるためにサッカーを利用したが、今回、怪我の痛みを少し遠ざけてくれたのも、ポルトガルのサッカーだった。
ポルトガルは準決勝でスペインに負けて、今回も優勝はなかった。いつも“あと少し”で届かない。「ファド」は日本語で、“運命”や“宿命”。今日の紙面にこれまでの“あと少し”が並べてあった。いつものように「これが宿命なのだから」。と素直に受け入れる彼らのファタリズモ(宿命感)が何とも愛しい。写真は横瀬浦で掲揚されていたポルトガル国旗。嬉しくなって、思わずポルトガル国歌を口ずさんだ。今回も訪れるであろうその“宿命”を予感しながら。