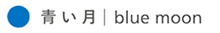ランドナーに乗るようになって、無性に写真を撮りたくなっていった。風景や光景を愛おしみたく、フィルムで。光を撮りたいので、モノクロかセピアで。ツァイスのレンズのいろいろを調べて、手に触れたり、撮った写真を見せて頂き、購入する寸前まで行ったのだけど、少しためらう。
それ相応のレンズを使えば、それなりに写るだろうけど、そういうのじゃないな、と。ランドナーも当初、見た目や評判からイギリス製のランドナーを選ぼうとしていたのだが、結局は、日本製のARAYAを。なので、カメラもやっぱり、しっくりくる日本製のをと、思って何となく宮本常一さんの本を眺めていたら、手にはカメラが。宮本さんは勿論、フォトグラファーではなく民俗学者だけども、宮本さんのその眼差しが、とても好きだ。なので、単純だけども宮本さんが愛したキャノネットかPENを探すことに(Sか、Dか、F、FT、どれにするかはこれから)。見ためや評判よりも、自分が愛着を持てるものを。“あこがれ”というものは、つくづく、自分を正直に、透明にしてくれるエッセンス。ランドナーにはしばらく乗れないが、東北にはフィルムカメラを持っていきたいと思う。