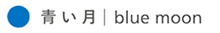とあるイタリア料理店でランチを。砕けすぎていない食感の残るトウモロコシの冷製スープに舌鼓を打った。そういえば妹たちはよく、トウモロコシを好んで食べていたな、と思い出し、「あ、トウモロコシ、食べたい」と、子どものように、思わず呟いた。「そうね、みつけたら、買おうか」と、妻。
それから、いっとき、夜のとばりが降りた頃、ふいにチャイムが鳴りドアを開けた。軒先には、思っていたけど、思いがけない人。「調子はどうかな?と思って。あ、それから、どうぞ」と、いつもの朴訥な語り口調で、ふいに、わさわさとしたビニール袋を前に差し出した。中に入っていたのは、穫れたてのトウモロコシだった。ト、トウモロコシ!と、まるで狐にでも騙されているようで、お昼に食べたいと言っていたところなんですよ、と、事の顛末を話す。「そう、それは良かった」と、驚く様子もなく、優しい表情を浮かべ、彼は颯爽と去っていった。
すこし贅沢と思いつつも、「実は、一度、丸かじりって言うものをやってみたかったんだ」と、妻に打ち明け、丸ごと一本、茹でてもらう。茹で上がったトウモロコシは、眩しいほどに光っていて、またもや贅沢と思いつつも真ん中からかじった。とても瑞々しく、果実を思わせるほど甘かった。今まで食べた、どのトウモロコシよりも美味しかった。よくわからないけども、元気も出て来た。
人生を左右するような怪我をして、わかったことがいくつかある。誰しも人に言えないような悲しみを抱えていて、同じような状況だと感じると、そっと、その秘密を打ち明けてくれるのだ。僕が知らなかっただけで、その悲しみを多くは見せず、当たり前に受け止め、前を向いて歩いておられたことを知る。そして、その悲しみは舐め合い、慰め合うものではなくて、分かち合うものだということも。もう、それからはそれ以上、そんなに言葉もいらなくなる。探り合う必要もなく、話さなくても充分に感じるようになってくる。僕のなにげなく、さりげない「今」がとても愛しいように、また彼(彼女)の人生も愛しい。気がつけば励まされているし、気がつかないところで励ましている(と、思う)。
彼がもし、よろめきそうになったら、飛び切り元気が出る物を携えていこうと思う。おおげさな雰囲気は出さなくていい。「そう、それは良かった」と、さりげなく差し出すのだ。