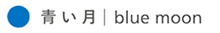妻に連れられ郊外へ。よせてはかえす波のように、おだやかな風にたなびく小麦の穂。凪いだきもちで、ぼんやりと眺めていたら、ふいに風向きが変わり、風が姿を現しながらこちらへやってきた。永かった五月も終わる。新緑と、薫風に包まれて自転車に乗る予定は変わってしまったが、それでもやっぱり、五月の風はやさしかった。
ストーブの炎を見つめていると、木の燃焼とは不思議だなと思う。二酸化炭素、水を大気に放出し、熱とほんのわずかな灰を残しながら、長い時を生きた木は一体どこへ行ってしまうのだろう。昔、山に逝った親友を荼毘に付しながら、夕暮れの空に舞う火の粉を不思議な気持ちで見つめていたのを思い出す。あの時もほんのわずかな灰しか残らなかった。生命とは一体どこから来て、どこへ行ってしまうものなのか。あらゆる生命は目に見えぬ糸でつながりながら、それはひとつの同じ生命体なのだろうか。木も人もそこから生まれでる、その時その時のつかの間の表現物に過ぎないのかもしれない。いつか読んだ本にこんなことが書いてあった。“すべての物質は化石であり、その昔は一度きりの昔ではない。生物とは息をつくるもの、風をつくるものだ。太古から生物のつくった風をすべて集めている図書館が地球をとりまく大気だ。風がすっぽり体をつつむ時、それは古い物語が吹いてきたのだと思えばいい。風こそは信じがたいほどやわらかい、真の化石なのだ”(イニュニック/星野道夫)