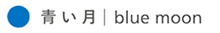保育園のアートディレクションを行うことに。これまで幾度か通い、先日、新しい園舎になるにあたり旧園舎のお別れ会が開かれました。園舎のこれまでとこれからを2回に分けて綴りたいと思います。園舎の設計・デザインは、『ワークス』さん。ワークスさんとはアルティアムで行われた北イタリア、レッジョ・エミリアの取り組みを紹介する展覧会以来の子どものプロジェクト。自ずと力が入ります。
長崎県諫早市で45年間、地域の子どもたちを育んできた「みやま保育園」。新しい保育園(工事完了後はこども園に)は、豊かな周辺環境を丁寧に読み取りながら、まちの中に象嵌されたように、保育室、ホール、学童などが分棟型配置で建つ計画が建てられています。先日、1期工事が完了し保育室や管理室などが使うことが可能になりました。これまでの園舎は建築的に見ると優れたものではないかもしれませんが、“使われ方”から見るととてもしあわせな建築だったことを、とても感じます。外の人間である僕も構わず包んでくれるような、ここを巣立った人たちの想い出にもためらわずに触れさせてくれるような、懐の広いやさしさがありました。

大きな楓が二本建ち、回廊のように、その二本の楓をどの部屋からも見渡せるよう、保育室が配置されています。肩を寄せ合った小さな家族(家庭)のような場所だから、得も言えぬ安心感を感じたのかもしれません。そして、ここの園はとても静か。モンテッソーリ園などに行くと、子どもたちは“お仕事”に集中していて静かなのですが、ここの静けさは何だろうなと考えていると、意図せずこの回廊型が、人の気配をいつも感じることで安心につながっているのかなと思ったり。諫早駅から徒歩圏内というのに、敷地内には多くの自然も残っています。湧き水は止めどなく溢れ、畑や原っぱでは虫達が日ごと宴を。裏山の木立からは、いつも清々しい風が吹いていて。敷地内のひとつの世界の中で、子ども達は四季のうつろいを、うららかに受け取っていました。また、敷地内には防空壕(洞窟)も。少し恐れを感じるその防空壕には今は、ナマズと鯉とイモリが住んでいて姿を見せたり、見せなかったり。でも、子どもの感受性を育むには、必ずしも子どもにとってやさしいものではなく、こんな畏怖な存在も大事(綴りながら想い出しましたが、この季節、湯本香津美さんの「夏の庭」を読みたくなります)。



建築的に見れば特筆すべきところは何もないかもしれない。けれども園舎は園舎としてただ機能するのではなく、子どもと大人、子どもと子ども、子どもと自然、そして自分と自分とをつなぐ場だとするのならば、こんなに幸せな園舎もそうないなあと感じました。そんな場所で開かれたお別れ会は、とてもあたたかく、うつくしい時間でした。ささやかで、さりげなくて、ありふれていて、おおげさじゃなくて、なんでもなくて。でも、愛を感じずにはいられなくて。そういったものが僕はとても好きです。触れさせてくれて、とても感謝しています。

お別れ会のプログラム

みんなで園の歌を。

建築家の坂口さんによる言葉は、とても温かかった。

解体ワークショップ。現場監督さんによる説明。

子ども達の手で。

想い出が遊び場に。

卒園した人たちも加わって

乳児室は迷路に。

子どもたちを見守ってきた楓の木

防空壕。子ども達のこちらと、あちらをつなぐ、扉。

風船の準備。

あ、

気を取り直して。みなさん、行渡りましたか?

グッグッ。大事なときに割れないのが、くす玉。

よいしょー!

サヨウナラ、サヨウナラ。

まだ見える、まだ見えると、子どもたち。

長い間、本当に本当にありがとう。