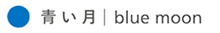賢治さんの故郷、新花巻駅で降り、賢治さんの足跡を辿りつつも観光地化された場所だけではなく、賢治さんが暮した普段の花巻を感じようと地図にない場所を歩いた。歩いた。歩いた。気がつけば随分と遠くまで歩いていて、さすがに焦り、地図を見た。どうやら山道に入ってしまったようで、所在がわからず、再び大きな道まで戻り、バス停もまず無さそうだったので、タクシーを呼ぶことにした。が、圏外…。それもそうだ。西日が差し始めたので、「あ、良かった。こっちであってる」と思いつつ、それは日暮れを意味していて、流石に冷汗が出て来て、焦燥感が身を覆った。「で、電話を借りよう」。にも、駆け込むような民家がなく、さらにしばらく歩いた。ようやく軒先で農作業をしているおじいさんを見つけたので、事の顛末を話した。するとおじいさんは、桑をかざしていた手を休め、「花巻駅まで送ってあげよう」と、思ってもいなかった言葉をかけて下さった。妻と顔を見合わせながら、そのご好意に甘えることにした。
三人がけのトラックに並び、花巻の町を案内してもらいながら、一路花巻駅まで。ガタンゴトンと揺れながら賢治さんのこと、震災のこと、三陸のこと、民家の形のこと、農業のこと、南部藩のことなど穏やかな岩手弁で話して下さった。風土にはやはり人も含まれるのだろう。東北がより身近に、より愛しくなっていく。「クーラー、壊れてて、すまんね」と、おじいさんが話すも、全開の窓から入ってくる花巻の風はこれ以上ない清々しさがあった。しばらく会話を続けていると、市街地に入ってきた。いつの間にか焦燥感は消え去り、まさに一期一会の切なさが込上げてきて、花巻駅が近づくほどに、もう少し駅が遠ければなどと、身勝手な感情が湧いてきた。だが、そうもいかず駅が見え始め、御礼を述べた。「また来ます」。それは偽りのない素直な気持ちだった。花巻駅に着きトラックを降り、深く頭を下げると、控えめなクラクションを一度ならし、おじいさんを乗せたトラックは、再び郊外へと帰って行った。